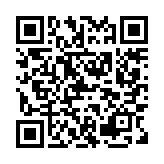令和7年4月13日(日)13時30分~14時50分 八代史談会定期総会
15時~16時半 第385回研修例会が行われました。
385回研修例会では八代史談会の会員でもある、八代文化財保護委員会委員長の高野茂氏による講演会がおこなわれました。
講演内容は「戦国期における相良氏の八代支配」で質疑応答の時間も含め、1時間40分にわたり、盛会裏に終了しました。
その後、18時より会場を移して、八代ホワイトパレスに於いて来賓の方々を含め懇親会が行われました。
私達、八代史談会は創設69年目を迎え、会員170名と共に年3回の会誌発行、年5回の研修例会を中心に地域の文化財・史跡の保存、研究などを後世に伝えるために日々、努力と研鑽を積み、活動をしております。
《八代市金剛干拓の旧堤防》
金剛干拓は主に八代市の名士である坂田家と八代城代松井家によって干拓されました。

*少し長くなりますが、八代史談会の歴史について述べさせて下さい。
■会誌題名由来 夜(や)豆(つ)志(し)呂(ろ)とは (倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)、牙子(やつ)世(し)禄(ろ)、牙子世六(やつしろ))
・歴史書に出ている古い「やつしろ」の名称を採用したいのが会員諸氏の希望であったので、平安中期、百科事典的分類による漢和辞典として知られた『倭名類聚抄』の中に出ている「夜豆志呂」を採用することになった。蒼露草に「牙子世禄」、図書編には「牙子世六」という言葉で紹介されている。
表紙の字は宮崎均氏の筆による。
■八代史談会創立60周年の回想 《会誌182号 松山丈三 現名誉会長寄稿文 一部抜粋》
―郷土やつしろの歴史と文化に寄与した活動の軌跡―
・本年(2016年)、八代史談会は創立60周年を迎えました。顧みると、八代市竹原町に熊本労災病院が建設(昭和28年本館完成)されることになりましたが、その建設工事中に数多くの弥生中後期や古墳時代の遺物が出土した。まさに古代史を変える大発見でした。
・昭和31年2月3日の肥後考古学会八代支部を結成に先立つ、昭和31年2月1日、内田辰雄先生は先述の大発見に伴う古代八代地方の貴重な史料の破壊、散逸を憂い、盛高靖博氏宅に有志8人が集まり、話し合い、発起人会を結成した。
・古代史に関心があられた熊本労災病院初代病院長の内田辰雄先生は、八代の郷土史に関心のある人達と話し合いを重ね、昭和31年2月3日,春光寺に於いて肥後考古学会八代支部を結成された。これが八代史談会の始まりである。
・当初は10数名の会員で発足し、初代会長に内田辰雄先生を選任した。
・昭和41年9月25日、会誌名を「牙子世禄」から「夜豆志呂」に改称した。
・昭和43年11月24日、志を同じくする者が郷土史研究に親しみやすい会名にしようと検討した結果、「八代史談会」と改称された。
・八代史談会は郷土史の研究、文化財や史跡の発掘、史跡文化財の見学、遺跡の保護保存、標木建立をはじめ、会誌「夜豆志呂」の発行、民俗文化の継承など地域文化の発展に貢献してきました。
一般的に地域の郷土史、文化時保護、保存活動の会は定着しにくいと言われますが、八代史談会は諸先輩方の多年の地道な活動の積み重ねで、今日まで連綿とその活動を継承してきました。
*なお、この回想寄稿文は9ページにわたるため、ここにすべてを掲載することは困難です。
会誌182号に全文が掲載されております。是非、御一読いただければ幸いです。